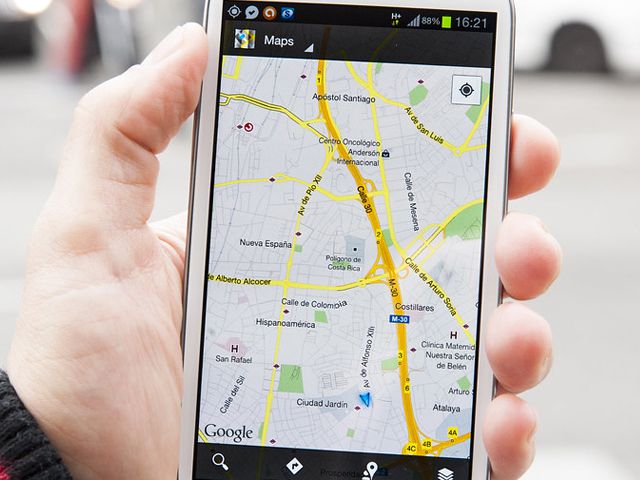ゼロトラスト(Zero Trust)とは、ネットワークセキュリティのアプローチの一つであり、従来のセキュリティモデルである「信頼のある内部ネットワーク」に依存せずに、すべてのアクセスを疑い深く評価するという考え方です。従来のネットワークセキュリティでは、パーミータ(境界)内のネットワークトラフィックに対しては信頼が置かれていました。しかし現代の複雑なネットワーク環境では、このような信頼を前提としたアプローチではセキュリティリスクが高まってしまいます。ゼロトラストのアプローチでは、ネットワーク上のすべてのトラフィックを信用せずに評価します。
つまり、認証、認可、暗号化、セグメンテーションなどのセキュリティコントROLSを適用し、個々のユーザーやデバイスがアクセスするたびに確認して評価します。これによって、ネットワーク内の異常なアクティビティや攻撃の兆候を検知し、適切に対応することができます。具体的なゼロトラストの実装には、いくつかの基本的な原則があります。まず第一に、すべてのアクセスは認証と認可が必要です。
すべてのユーザーやデバイスは、アクセスする前に正当性を確認され、適切な権限を持っているかどうかが評価されます。これによって、不正なアクセスを未然に防ぐことができます。第二に、アクセスは最小特権の原則に基づいて制御されます。ユーザーやデバイスには、必要最低限の権限しか与えられません。
これによって、悪意のあるアクティビティが発生した場合でも、被害を最小限に抑えることができます。第三に、全体のネットワークをセグメント化します。セグメンテーションによって、ネットワーク内のリソースが必要な範囲に制限され、不正アクセスからの被害を最小限にしながら、セキュリティを向上させることができます。さらに、ゼロトラストでは、アクセスの監視と分析も重要な要素です。
ユーザーやデバイスのアクセスパターンや異常な振る舞いを検知し、早期に対処することができます。また、AIや機械学習を組み合わせることで、より効果的なセキュリティ対策を実現することができます。ゼロトラストのアプローチは、ITセキュリティを強化するだけでなく、クラウド環境やモバイルデバイスなどの新しいテクノロジーを柔軟にサポートすることも可能です。また、境界を越えたアクセスや遠隔ワーカーへのセキュアなアクセスも実現できます。
最近では、セキュリティの脅威がますます高度化しているため、ゼロトラストのアプローチはますます重要性を増しています。ネットワークセキュリティにおけるゼロトラストの原則とアプローチを理解し、実践することは、企業や組織にとって不可欠な要素となっています。ゼロトラストは、従来のセキュリティモデルに依存せずに、すべてのアクセスを疑い深く評価するネットワークセキュリティのアプローチです。従来の信頼のある内部ネットワークではなく、認証、認可、暗号化、セグメンテーションなどのセキュリティコントロールを適用して個々のユーザーやデバイスのアクセスを評価し、異常なアクティビティや攻撃の兆候を検知することができます。
ゼロトラストの実装には、認証と認可の原則、最小特権の原則、ネットワークのセグメント化、アクセスの監視と分析が重要な要素となります。ゼロトラストは、ITセキュリティを強化するだけでなく、クラウド環境やモバイルデバイスなどの新しいテクノロジーをサポートし、境界を越えたセキュアなアクセスを実現することができます。最近の高度化するセキュリティ脅威に対応するため、ゼロトラストの原則とアプローチの理解と実践は企業や組織にとって不可欠です。ゼロトラストのことならこちら